朝晩がめっきり秋らしくなってきました。
来週の月曜日は十五夜だそうですね。
たまちょび地方の天気予報は雨のち曇り。
お月様は見られそうにないです。
十五夜=満月ではない?!
恥ずかしながらこの歳まで十五夜といえば満月だと思っていました。
だってお団子とススキを飾ってまん丸お月様を愛でるんでしょ?

旧暦の「中秋」に昇る月が一年で最も美しいことから「中秋の名月」と呼ばれるようになったらしいです。
そして、月の満ち欠けの変動から今年の満月は翌日の10月7日だそうです。
お月見の由来
そういえばお月見について、なんとなくの感覚でのイメージしかなかったので、ちょっと調べてみました。
遡ること平安時代、中国から伝わってきたと言われています。
当時は貴族文化として宴を楽しんだようですが、江戸時代には庶民にも広まっていって、農作物の収穫への感謝を伝える意味に変化したようです。
そこから秋の実りに感謝して、稲穂に見立てたススキと満月に見立てたお団子を飾って月を愛でる行事として定着したそうです。
当時の「中秋」はまだ稲刈り前の時期でもあって、稲穂に似ているススキが選ばれたんですね。
ススキは切り口が鋭いので、悪いものから農作物を守り翌年の豊作を祈願するという説も。
日本の古くからの行事は、やっぱり農耕に関係する物が多いですね。
古き良き日本の風習

日本の(いや外国でも)年中行事にはちゃんと意味があって、感謝や願いが込められているんですよね。
年を取ったせいですかね?自然とか古い行事とか神社仏閣とか、若い頃より興味を持ちはじめました。
残念ながら私は、縁側のある家に住んだことがないので、いわゆる典型的な「お月見」をしたことがありません。
せっかく由来まで調べたんだし、キレイな月を眺めてみたいものですが、今年は無理そうで残念です。
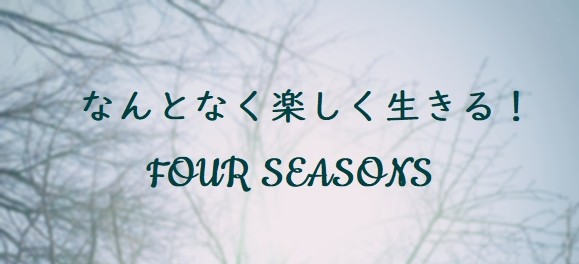
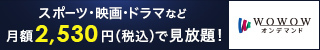
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44c8ea9f.badff49e.44c8eaa0.5bb973c3/?me_id=1280285&item_id=10000084&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnet-makino%2Fcabinet%2Fproduct_image%2F5510_thumbnail.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/40484e6b.7926df19.40484e6c.50a20475/?me_id=1323027&item_id=10000213&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fcascata%2Fcabinet%2F05066659%2F05066661%2Fimgrc0072657881.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/404860cb.7c29666b.404860cc.cd6b30f9/?me_id=1261122&item_id=11281928&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F502%2F405502.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/40485999.74c60aef.4048599a.30f0bb66/?me_id=1345661&item_id=10254759&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyo-sake%2Fcabinet%2F01%2F16%2F880015x01a880018x01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/483087de.3b719c97.483087df.5fc014d2/?me_id=1222208&item_id=10185403&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flivingut%2Fcabinet%2Fmaker_jej7%2Funi416801.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/50590725.c115dc34.50590726.7e3ead81/?me_id=1209747&item_id=10001789&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffkikaku%2Fcabinet%2F03574889%2F05592893%2Fimgrc0103946198.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)